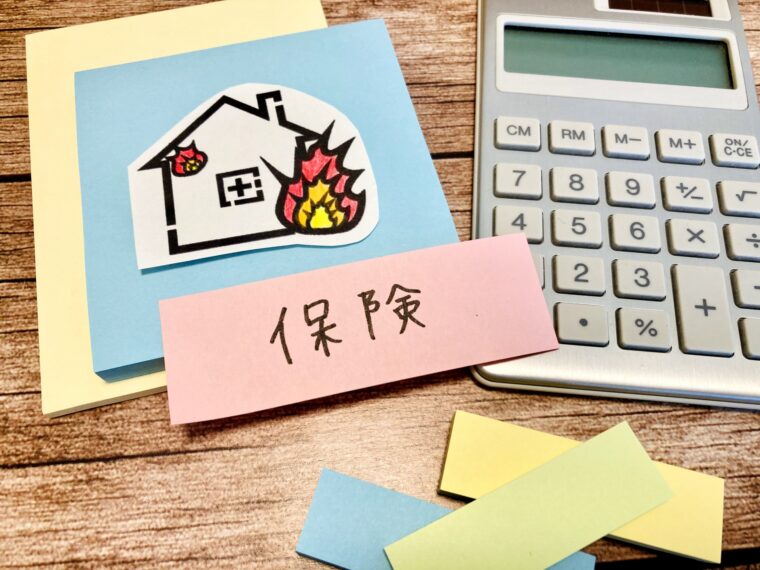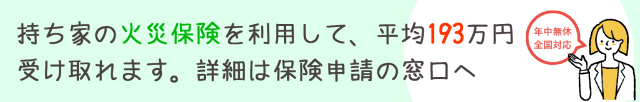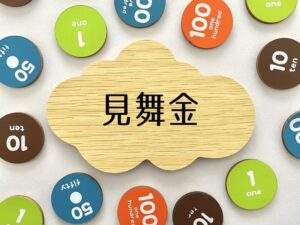家を建てたり、引越しをしたりすると「火災保険」への加入を検討しますよね。火災保険は、いざという時のトラブルからリスクを回避するために重要ですが、補償内容が多いため複雑で、どんな補償内容にすればいいか悩みます。
この記事では、火災保険の必要性や注意点、基本的な火災保険の補償内容について説明し、補償内容を選ぶ際の重要なポイントについても解説します。最後まで読んで、あなたに合った適切な補償内容を選びましょう。
火災保険のメリット
火災保険には、以下のようなメリットがあります。
- 自然災害によって資産が失われることをカバーできる
- 家財の破損にも備えられる
- 補償内容をカスタマイズできる
まずは、これらについて詳しく解説します。
自然災害によって資産が失われることをカバーできる
火災保険は、火災による被害だけでなく、自然災害や不測かつ突発的な事故による損害にも対応しています。日本では台風や豪雨などの自然災害が頻発し、これらの災害によって資産が失われるリスクがあります。火災保険に加入することで、自然災害による損害にも十分な補償を受けることができ、安心感が得られます。
家財の破損にも備えられる
火災保険は建物だけでなく、家財にも補償をつけることができます。災害や事故によって家具や家電が損傷・破損した場合、火災保険によって一定の補償が受けられる可能性があります。自然災害だけでなく、盗難の補償もあります。高額な家財が失われた際に、その一部を補償してもらうことで、再度購入する際の経済的な負担を軽減できます。
補償内容をカスタマイズできる
火災保険は補償内容を柔軟にカスタマイズできるため、自分のニーズに合わせて最適なプランを選択することができます。例えば、建物や家財の保険金額や補償内容、地震保険の有無などを調整することで、不要な補償対象を排除し、必要なリスクに対処することが可能です。この柔軟性は、火災共済と比較して特に大きなメリットとなります。
火災保険のデメリット
火災保険には、メリットだけでなく下記のデメリットがあることにも注意が必要です。
- 一戸建ては保険料が高くなる
- 補償内容によっては保険料の負担が大きくなる
これらのデメリットについて、詳しく解説します。
一戸建ては保険料が高くなる
火災保険は、住宅の形態(構造、面積、築年数、耐震性など)によって保険料に違いが生じます。一般的に、一戸建て住宅の場合は保険料が高くなる傾向があります。マンションなどの共同住宅の場合に比べ、同等の補償内容であれば5年間で4〜5万円ほどの違いが生じることがあります。一戸建ては面積が広く、補償が広範囲にわたるため、火災のリスクが高まると考えられます。それに伴って保険料も上昇する傾向が見られるのです。
参考:損保ジャパン
補償内容によっては保険料の負担が大きくなる
火災保険のデメリットとして、補償内容が充実するほど保険料が高くなる可能性があります。特約やオプションを追加して補償範囲を広げることで、災害や事故に対する補償が充実しますが、同時に保険料も増加します。保険料の負担を軽減するためには、必要最低限の補償内容を検討し、無駄な特約を避けることが重要です。適切なバランスを見極めることが必要です。
火災保険の補償内容
火災保険は、以下のトラブルに対して補償する保険です。
- 火災・落雷・破裂・爆発
- 風・雹(ひょう)・雪
- 水害・土砂崩れ
- 落下・飛来・衝突
- 暴力行為
- 盗難
- 突発的な事故
これらの補償内容について、詳細に説明します。
火災・落雷・破裂・爆発
「火災」は、建物や家財が火災により損傷した場合の補償を指します。これには、失火、延焼、ボヤなどが含まれ、火元によらず発生した火災に対する補償が期待できます。隣家から燃え移った火災についても、ご自身の火災保険で対応します。
「落雷」は、雷による損害が対象です。建物や家財が雷により損傷した場合、保険金が支払われます。具体的な事例として、雷が家屋に直撃して損傷が生じたり、雷により電化製品が故障した場合などが挙げられます。
「破裂・爆発」では、ガス漏れやその他の事故により建物や家財が破裂または爆発した際に補償が適用されます。例えば、ガス漏れによりキッチンが爆発し、建物や付属品が損傷した場合、火災保険は損害に対して補償を提供します。
参考:日新火災
風・雹(ひょう)・雪
「風」は、強風や台風による被害が対象となります。例えば、屋根の瓦やスレートが強風で飛ばされるなどの被害がこれに該当します。
次に「雹(ひょう)」についてです。大粒の雹が降り注ぐことにより発生する損害が対象です。雹が窓ガラスを割ったり、カーポートや屋外設備にダメージを与える場合に補償します。
「雪」に関しては、大雪や雪崩による被害が補償対象です。例えば、豪雪により屋根が倒壊したり、雪崩が発生して家屋に損傷が生じた場合に補償されます。
参考:損保ジャパン
水害・土砂崩れ
「水害」に関しては、台風や集中豪雨によって発生する洪水や高潮、それに伴う家屋の浸水被害が対象です。火災保険は、これらの水害により建物や家財が損傷した場合に、補償を行います。例えば、床上浸水による床の損害や、流されたり水没した家財に対して、修理や再購入にかかる費用を支援します。
「土砂崩れ」は、急激な雨による山地の崩壊が原因で生じる被害が対象です。土砂崩れにより建物や家財が損傷した場合、その修復や復旧に伴う費用を補填します。例えば、土砂によって家屋が押し流されたり、家財が埋もれてしまった場合を指します。
参考:ソニー損保
落下・飛来・衝突
「落下」は、建物外部から物体が地上に落ちてきて建物や家財に損傷を与えた場合が該当します。例えば、木の枝や建物の一部が崩れてきて窓ガラスが破損したり、落下したドローンが屋根や車庫に衝突して損傷が生じた場合を言います。
「飛来」については、外部から飛来した物体が建物や家財に衝突し、損傷を引き起こした場合が対象です。例えば、自動車が跳ねた石が建物に衝突して外壁が損傷したり、窓ガラスが割れた場合を言います。
「衝突」は、自動車や他の物体が建物や家財に衝突して損傷が生じた場合が対象です。例えば、自動車の車庫入れに失敗して建物にぶつかり、外壁や柱が損傷したり、外部からの衝突により家財が損害を受けた場合です。
参考:損保ジャパン
暴力行為
火災保険は、集団行動や騒擾などに伴う損害に対しても補償されます。例えば、労働争議やデモによる暴動が発生し、これによって建物や家財が損害を受けた場合をいいます。
盗難
盗難補償では、家財や建物が盗人によって破損させられたり、盗難された場合に補償を行います。具体的には、空き巣や不法侵入者によって物品が盗まれ、または建物が侵入によって損害を受けた場合を言います。
突発的な事故
突発的な事故による補償では、日常生活の中で予測困難かつ突発的に発生するさまざまな事故に対して補償をします。うっかり物を落として壊したり、犬や子どもに壊された場合など、あらゆる破損や汚損が含まれます。
例えば、子供が室内で遊んでいる際にボールをテレビに当てて壊してしまったり、掃除中に掃除機をドアにぶつけてしまいドアが破損するなどが考えられます。
対象となる損害は、外観上の損傷や汚損であっても、その機能に支障をきたすようなものであれば、補償の対象となる場合があります。ただし、すり傷などの損傷で機能に支障をきたさない場合は補償の対象外となるので注意しましょう。

火災保険の補償内容の選び方
火災保険の補償内容を選ぶ際には、以下のポイントを抑えることが重要です。
- 補償対象を決める
- 保険金額を決める
- 補償内容を決める
- 地震保険付帯の有無を決める
- 保険期間を決める
これらのポイントについて、詳細に解説します。
補償対象を決める
まずは、補償対象を「建物のみ」か「家財のみ」か「建物+家財」かを選ぶ必要があります。
賃貸物件の場合は「家財のみ」が一般的です。
持ち家の場合は「建物のみ」「家財のみ」「建物+家財」から選択しますが、「建物+家財」が一般的です。
建物
建物の補償対象は、家のほかに下記も含まれます。
・門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物
・畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備など
参考:損保ジャパン
家財
家財とは、設定した所在地内の家屋に収容されている家電や家具などを指します。
物置や車庫などの付属建物に収容されている家財も対象となります。あた、敷地内にある宅配物、自転車および原動機付自転車も補償されます。
高額貴金属に対して高額な補償を設定する場合は、「明記物件」として契約時に明示が必要となります。家財は、持ち家に限らず賃貸でも重要な補償です。
参考:損保ジャパン
保険金額を決める
続いて、保険金額を設定する必要があります。
なお、保険金額は、建物と家財に対して次のようなポイントで決定します。
建物
建物の「保険価額」は「新価」「時価」の2つがあります。最近では新価を基準に設定することが一般的です。
新築物件の場合は売買契約書を参考に設定します。中古物件の場合は、新築時の建物代金と建築年月を参考にする方法と、構造や建築年月、面積で設定基準を割り出す方法があります。
一方で、経年減価分を差し引いた現在の価値が時価です。時価で設定してしまうと、いざという時に補償が足りない可能性が高いため、新価設定が推奨されています。
参考:ソニー損保
家財
家財に対する保険金額は、保険会社のサイトで提供される「家財簡易評価表」を参考にすることができます。実際の家財価格を積算する方法が的確ですが、もし分からない場合は家族人数などで算出することもできます。適切な補償金額を設定しましょう。
補償内容を決める
保険金額を決定した後は、補償内容を検討します。
火災、落雷、破裂・爆発、風災などの基本補償に加え、水災、盗難、水漏れ、破損・汚損などのオプション補償も考えましょう。自分の住まいやライフスタイルに合った補償内容を選ぶことが大切です。
住まいの構造や構造階級別も見逃せません。保険料と補償のバランスを考えつつ、必要な補償を見極めていくことが重要です。
地震保険付帯の有無を決める
次に、地震保険付帯の有無を決めます。火災保険では地震は補償内容に含まれないため、地震による火災や、津波による被害は補償されません。そのため、地震保険を付帯することを検討する必要があります。
地震保険の付帯有無を決める際には、まず住んでいる地域の地震リスクを考慮します。地震の頻度や規模が高い地域では、地震保険の加入が重要です。また、建物の構造や耐震性も考慮し、耐震補強が十分でない場合は、地震保険の付帯を検討します。
参考:日本損害保険協会
保険期間を決める
火災保険の保険期間を決める際には、将来のライフプランや住まいに関する変化を考慮することが重要です。一般的に、長期契約は割引率が高くなりますが、住まいの変更や引っ越しが予測される場合は短期契約を検討することも可能です。
現在、一般的な保険会社では保険期間「5年」が最長です。
長期契約のメリットは、保険会社の料率改定の影響を受けないことや、手続きの簡略化にあります。特に、昨今は毎年のように料率改定が行われ、築古物件に対する保険料が高騰しているため、長期契約によって保険料を抑える方法を選択する方が多いです。
短期契約は1年ごとに契約更新が必要で手間がかかりますが、その都度補償内容を見直す機会があり、変化に合わせた補償を選択できます。
賃貸物件などで短期間の居住を予定する場合は、1年未満の短期契約も可能です。ただし、保険会社や商品によって契約期間に関する条件が異なるため、注意が必要です。一般的には、長期契約を考える際はライフプランを見据えつつ、将来の住まいについての見通しを立ててから選択することが重要です。
参考:損保ジャパン
火災保険によくある質問
最後に、火災保険によくある質問に対して回答します。
Q. もらい火で火事になった場合も補償されますか?
もらい火の場合、一般的には賠償を補償してもらうことができません。失火法により、火元に過失がない限り賠償責任が発生しません。そのため、もらい火の被害者は、自分の火災保険を利用することになるので注意しましょう。
参考:日本損害保険協会
Q. 所得控除の対象になりますか?
火災保険は、基本的に所得控除の対象にはなりません。2006年の税制改正により、損害保険料控除が廃止され、現行の火災保険は対象外となりました。
しかし、地震保険は控除の対象となります。地震保険料控除証明書が発行されますので、申告手続きまで大切に保管してください。
参考:ソニー損保
Q. 途中解約はできますか?
火災保険は途中解約ができますが、一括払をしている場合には損をする可能性があります。未経過保険料が戻るものの、全額は戻りません。また、解約には保険会社への連絡と必要書類の提出が必要で、電話だけでは解約が難しいとされています。
参考:損保ジャパン
Q. 共同名義の建物の場合、誰を契約者にすればいいですか?
共同名義の場合、所得の高い人を契約者にするのが一般的です。地震保険が付帯している場合、所得が高い人が契約者であれば地震保険料控除により所得税・住民税の負担が軽減されます。そのほか、契約手続きをスムーズに行える人を契約者とする場合や、保険料を支払う人を契約者にするケースが多くあります。
参考:あいおいニッセイ同和損保
まとめ
この記事では、火災保険の補償内容を選ぶ上で重要なポイントを解説しました。補償内容を検討する際は、補償対象や保険期間などを将来のライフプランや状況に合わせて検討し、妥当な保険料と補償内容に調整する必要があります。適切な火災保険に加入し、安心して住める家を目指しましょう。