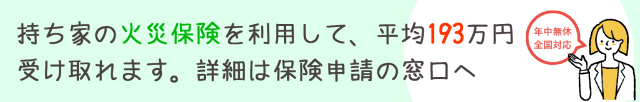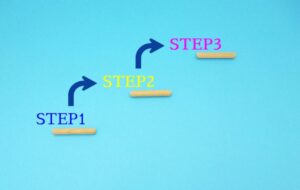火災保険を申請する手続きは、慣れていないと複雑なので、「自分でやるものなの?」と疑問に思う方もいます。この記事では、火災保険が自分で申請できるか、自分で申請するとしたらどのようなポイントを押さえる必要があるか、ということについて解説します。自分で火災保険を申請するのが不安だと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
【結論】火災保険の申請は自分でもできる!
火災保険の申請は難しい印象がありますが、実際には自分で行うことができます。ネット上では難易度が高いとの声も聞こえますが、外部に依頼すると手数料が発生します。例えば、100万円の給付金なら30万円から40万円の手数料がかかりますが、これは決して安い金額ではありません。
しかし、費用を抑えつつも自分でできるならば、火災保険の申請を個人で行うことが理想的です。もちろん、手間はかかりますが、結論としては可能です。火災保険の申請を自分で行うために必要な基本的な知識や道具、書類、手続きについて、ここから詳しく解説していきます。
火災保険の給付金をもらえるケース・もらえないケース
火災保険の給付金は、全てのケースでもらえるわけではありません。ここからは、火災保険の給付金がもらえるケースともらえないケースの違いについて解説します。
給付金をもらえるケース
火災保険の給付金がもらえるのは、日常生活において発生する突発的な事故に対する補償を提供するためです。具体的には、火災・風水害・地震・盗難などがこれに該当します。
給付金が支給される条件は、保険契約の補償範囲内であり特に自然災害などの偶発的な事故が発生した場合に該当します。例えば、2019年のデータでは風災・ひょう災が最も多く、50万件以上の支払いがあり、その総額は4兆円に達しました。水災も約1兆円の支払いがあり、大規模な自然災害による被害が顕著です。
これらのデータからも分かるように、給付金がもらえるケースは火災保険の補償範囲内で発生した突発的な事故であり、特に風災・水災などが最も多く支給されていることが示されています。最新の情報を確認し、適切な補償を受けることが大切です。
参考:損害保険料率算出機構「2020年度 火災保険・地震保険の概況」
給付金をもらえないケース
火災保険の給付金がもらえないケースにはいくつかのポイントがあります。まず、経年劣化や老化による損害は火災保険の適用外となります。火災保険は突発的な被害に備えるものであり、徐々に進む経年劣化は補償対象外です。保険会社の調査で経年劣化と判断されると、給付金はもらえません。
また、故意的または重大な過失による損害も補償されません。契約者の故意や重大な過失によって発生した損害は、保険法第17条に基づき補償対象外となります。例えば、台所での火災を避けるべく注意が必要な状況で放置した場合などが含まれます。
さらに、風災・ひょう災・雪災の修理代金が20万円以下の場合も注意が必要です。一部の契約は修理が20万円以上でないと補償しない規定があります。修理費用が20万円以下の場合、その修理代金は全額自己負担となりますので注意が必要です。見積りがこの基準を満たしているか確認することが重要です。
火災保険を自分で申請する際に失敗しないためのポイント
火災保険の申請に慣れない場合、申請しても書類の不備などで申請の修正を要求されることがあり、最悪の場合はそれによって給付金がもらえなくなってしまいます。ここからは、申請に失敗しないために押さえておくべきポイントについて解説します。
高所の被害状況を忘れずに
火災保険の申請には、被害状況の詳細な確認が必要です。特に屋根や高い箇所では、状況確認が困難になりますが、屋根や高所は被害が発生しやすい部分でもありますので、確実に確認すべき箇所でもあります。
なお、屋根や高所の被害状況を確認する際、伸ばし棒を利用することが有効です。「伸ばし棒(自撮り棒)」を使うことで、屋根や高い箇所の撮影が可能になります。ちなみに、ドローンは飛行に許可が必要であり、横風に弱く事故のリスクがあるため、おすすめできません。伸ばし棒を使用することで、自分で屋根上や高所の被害状況を確認することができます。
伸ばし棒を使って高所の被害状況を確認する方法はさまざまですが、例えば7m以上の伸ばし棒を使って撮影する方法や、2階のベランダから伸ばし棒を使って撮影する方法があります。
ただし、危険が伴いますのでプロの業者に依頼できる場合はお願いしましょう。安全で確実な方法を選び、高所の被害状況を見逃さないようにしてください。
必要書類を全て揃える
火災保険の申請には、必要な書類を作成して提出する必要があります。一般的には、被害の復旧に関する見積書や被害箇所の写真、被害の状況を説明する書類(保険金請求書や落雷証明書など)が求められます。
修理見積書や被害写真は修理業者に用意してもらえることが多いため、契約者が準備するものは保険金請求書などです。保険金請求書は請求者の情報や支払先口座、事故の詳細を記入するもので、簡単に作成することが可能です。
必要書類が不足していないかや、記載方法がわからない場合には、契約している保険会社に連絡して詳細な疑問を解決してから書類作成に取り掛かりましょう。

請求期限を守る
火災保険の申請において、請求期限を守ることは重要です。保険法第95条により定められた請求期限はどの保険会社も同様であり、火災保険の給付金を請求する権利や保険料の返還請求権は、その行使を開始してから「3年間」が有効期限とされています。この期限を過ぎると保険金の請求権は時効によって消滅してしまうため、注意しましょう。
この期限を守らない場合、たとえ保険代行業者に依頼していても、保険金の請求が認められなくなります。つまり、期限を過ぎればどれだけ準備が整っていても保険金を得ることはできませんので、請求期限を守ることは大切です。火災保険の給付金を受け取るためには、期限内に請求手続きを完了させることが必須となりますので、注意が必要です。

適用範囲を正しく把握する
自分が加入している火災保険の内容と適用範囲を正しく把握することは、火災保険の給付金を請求する上で重要です。
例えば、台風による被害ならば「風災」、地震による被害ならば「地震保険」に加入している必要があります。保険証券を確認するのが最も手っ取り早い方法ですが、証券を紛失した場合でも安心してください。保険会社に連絡すれば、現在加入中の補償内容を教えてもらえます。
自分の保険がどのような災害に対応しているかを理解し、必要な補償範囲に加入しているか確認することで、適切な請求手続きを行うことができます。保険の専門的な相談も受け付けているので、疑問点があれば積極的に保険会社に問い合わせることが大切です。
火災保険を自分で申請する方法
ここからは、実際に自分で火災保険を申請する場合の手順について、5つのステップで解説します。
補償内容を確認する
まずは、加入している保険の補償内容を正確に理解することが不可欠です。火災保険は保険会社によって異なる補償が提供されているため、他の人が受けた補償が自分にも適用されるわけではありません。
なお、補償内容は保険証券に明記されているケースや、補償内容確認のための書類が送付されるケースがあります。確認すべきポイントは、被害の原因や補償対象の部分、補償される金額の範囲(免責金額)です。
補償内容がわからない場合や保険証券がない場合は、電話で保険会社に直接問い合わせることも可能です。自分の家に適用される補償内容を正確に把握しておかなければ、申請すべきものかどうかも判断がつかないため、はじめに確認しておきましょう。

被害箇所の写真を撮影する
保険金の請求に必要な写真は、被害を受けた建物や家財の全体が入っている写真、損害が生じた状況を確認できる写真など数枚が必要です。
これらの写真は、建物全体や損害箇所に焦点を当て、複数の角度から明瞭に撮影するようにしましょう。写真は修理業者が撮影したものでも構いませんが、自ら撮影する場合は注意が必要です。例えば、屋根の損害など高所の写真は自身で撮影するのは危険ですので、安全を確保した修理業者に頼むことが賢明です。
保険会社に連絡する
状況が確定したら速やかに保険会社に連絡をとり、火災保険の申請書類を入手することが重要です。保険会社によって申請に必要な書類が異なるため、各保険会社のフォーマットを確認する必要があります。
状況が整ったら、迅速に保険会社に電話やメールで連絡し、申請書類の送付を依頼しましょう。具体的な手続きや必要な情報について教えてもらえます。
修理の見積書を作成する
申請書を受け取った後、修理の見積書を用意する必要があります。見積書は各損傷箇所の修理業者に依頼して取得できますが、以下の注意が必要です。
修理業者が作成する見積書が、火災保険が必要とする見積書と異なる場合があります。火災保険の申請に必要な見積書は、被害の程度や元に戻すための費用を詳細に示すものでなければなりません。現場での材料の入手難易度や提案の変更点など、内容に一貫性がないと、再提出を求められたり、給付金が減額される可能性があります。注意深く見積書を取得し、正確で詳細な内容を含むよう注意しましょう。
申請書に必要事項を記入して返送する
申込書が到着したら、必要な情報を丁寧に記入して、必要書類を添付して送り返しましょう。申込書は原則として契約者本人が記入する必要があります。保険会社によっては、被害箇所を示すために見取り図を描いて提出するよう求められることもあります。
見取り図の作成が未経験の場合、少し苦労することもあるかもしれませんが、保険会社から提供される用紙を使用し、サンプルを見ながら慎重に作成しましょう。また、提出前に内容を再確認し、漏れのないよう心がけましょう。

まとめ
火災保険の申請を自分で行うことは、慣れていない人には苦労の多い作業ですが、いくつかのポイントを押さえておくことで失敗せずに申請することができます。この記事にあるいくつかのポイントを確認し、確実に給付金をもらえるように慎重に申請しましょう。